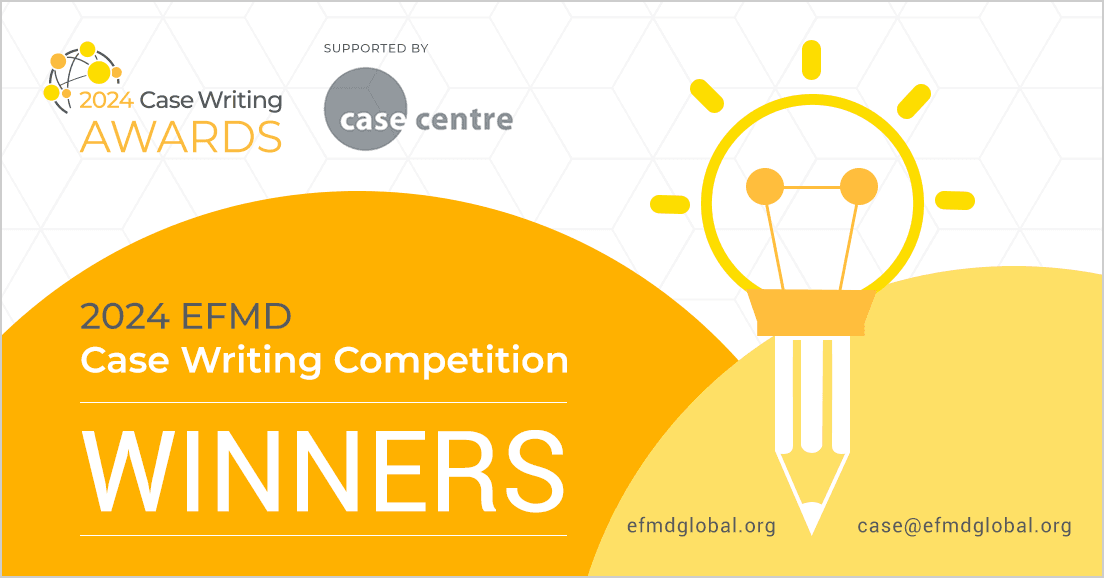このブログの執筆者:平岡 杏菜(ひらおか・あんな)。三井物産入社後ウェルネス事業部で医療事業の投資案件に携わった。2018年10月から2020年9月までの2年間、Moon Creative Labに出向。ヘルスケアスタートアップに挑戦した後、三井物産ウェルネス事業部へ帰任し、その後人事総務部へ異動。D&Iを推進する業務を経験し、2023年から再度Moonへ。現在は、Senior L&D specialistとして活躍。新規事業創出プログラムなど、社内外に向けたワークショップでファシリテーターを務める。
ミーティング、セミナー、ワークショップのファシリテーションをしたことはありますか?
私にとってファシリテーションとは、参加者が創造性を解き放てるよう適切にガイドし、参加者に力を与えるアートです。
私はこの1年間、およそ30超のワークショップでファシリテーションを担当してきました。向き合ったのは、10か国以上の様々な国々から参加した500名を超える人々です。その経験から、ワークショップ成功のヒントや、参加者の主体性を高める「ファシリテーションの鍵」となる要素に気づきました。
1.ファシリテーターは「方位磁針」。船長ではない

ファシリテーターの役割は、参加者に考えるための材料を提供することと言えます。
つまり、決定権は参加者にあるということを理解する必要があります。その船の船長はあくまで参加者であるということです。船のかじをとるのは参加者です。
ファシリテーターの役割は、彼らの手を止めることなく、その旅に力と自信を与えることにあります。なぜでしょうか?
私自身の失敗談として、ある参加者とのやりとりを例として紹介しましょう。
失敗談:反射的な課題の解決が裏目に
ここでは、ビジネスアイデアの具現化プログラムの例を紹介します。このプログラムは新規事業開発のために開発されたもので、社会課題の定義、ソリューションアイデアの具体化、ウェブサイトの立ち上げなどを5日間かけて行うものです。
あるとき、参加者の一人が社会課題についてリサーチをしている際、インサイトを収集するためのインタビューに必要な人選で迷っていたことがありました。そのとき、私は参加者に候補をいくつか伝えたのですが、私の提案から影響を受けすぎたせいか、本人が腑に落ちていないままインタビューをした結果、思うようなインサイトが得られなかったようでした。
私はほかにも可能性のある候補者が思い浮かびましたが、問いかけによって参加者自身のアイデアを引き出すことにしました。
「同じような課題に直面したことのある人はどんな人だと思いますか?」
「インタビューでどんな質問をすればもっと深く経験を語ってもらえそうですか?」
すると、それまで行き詰まっていた参加者が、突然前のめりに行動しはじめたのです。ペルソナのブレインストーミングや、幅広くインサイトを得るための質問作成から始め、さまざまな検討を主体的に計画して次々と試していきました。
これは、答えを教えることだけが適切なガイドではないことを示す一例と言えます。参加者が自らの意思で船のかじを取るためには、ファシリテーターからの問いかけに大きな意味があったのです。
成功体験:共感と対話が参加者に変革をもたらした
こうした問いかけの重要性から、私はファシリテーションの鍵が「共感」と「対話」にあるのではないかと考えています。そのため、私は参加者とより深く繋がるために、まず「誰もが安心して発言できる空間」を大切にしています。そのためには「決まった答えはない」と思ってもらえる環境づくりが極めて重要です。
そのうえで、参加者が「自分の話を聞いてもらえている」「自分のことを考えてくれている」と感じられれば、心の扉が開き、自然と勇気を出してチャレンジしようと思えるはずです。それが行き詰まっているときであればなおさら、参加者に共感し、問いかけることが、次の一歩を踏み出す力になります。
私はプログラムで課題の定義に行き詰まっていたある参加者に対して、結論を急がずこう問いかけたことがあります。
「プログラムに参加してみて、今はどんな感情がめぐっていますか?」
「設定した課題に対して、今はどう感じていますか?」
私は彼に共感しようと、感情に訴える問いかけをしました。彼は、結果ではなく感情に対する質問を受けたことに驚いていましたが、これをきっかけにして私とのメンタリングセッションを新たに設けるなど積極的に新しい方向性を模索しはじめ、心を開いてくれたようでした。
そして、課題の定義も終わり、ワークショップが7割ほどまで進捗したとき、彼はこんな相談を持ちかけてきました。
「申し訳ありません。どうしても今向き合っている課題に情熱が持てず、最初からやり直したいです」
私はこう答えました。
「正直に話してくれてありがとうございます。謝らないでください。情熱を持てる課題を一緒に探索しましょう!」
この切り替えがまた彼の心に火をつけました。その後、ものすごいスピードで課題の選定をイチからやりなおし、自信を持って最後のピッチまで一気に駆け抜け、最終的にはトップパフォーマーに数えられるほどの結果を残したのです。

「ワークショップ後半でも引き返していい」と思ってもらえたのは、「誰もが安心して発言できる空間」や「決まった答えはないという前提」を共有できた結果だと思っています。
彼は、私が感情に寄り添って対話しようとしたことに感謝してくれました。今でも連絡を取り合っていますが、その度に共感の力を思い知らされます。
参加者に共感し、問いかけ、対話するなかで使われる一つひとつの言葉には、参加者の目に輝きを灯す魔法とも言えるような力があるのではないでしょうか。
2.遊び心のある演出と小道具が「非日常的体験」をつくる

これまで、ワークショップにおけるファシリテーターの役割や、共感と問いかけの力がいかに参加者のモチベーションに影響するかについて紹介しました。しかし、当然ワークショップの具体的な内容も結果に大きな影響を与えます。
なかでも強調したいのは、遊び心のある工夫の必要性です。私は、参加者をリラックスさせ、創造性を開花させるために、いつも遊び心のある要素を盛り込みたいと考えています。
手触りのある創造的なアクティビティは、日常に追われて疲弊している脳を活性化してくれるはずです。おもちゃのブロック、ラフな絵で描くストーリーボード、ポスト・イット®やステッカーで作るプロトタイプは効果的な一例です。遊び心のある作業はただ楽しいだけではありません。既成概念にとらわれずに物事を考えるための環境を作るということにつながります。
とくに、長時間プログラムに取り組む必要のあるワークショップでは、最後まで走り切るためのカンフル剤として、遊び心ある演出や仕掛けが大きな意味を持ちます。具体的な実例を紹介しましょう。
手作り小切手で最後のピッチを盛り上げる
ここでは、社会課題の定義からソリューションや市場参入戦略を含むピッチの構築を目的としたワークショップの例を紹介します。このワークショップは、数日間の学習プログラムを経てアイデアを具体化し、最終日のピッチでビジネスアイデアを発表して終了します。
丸2日かけて行われていたワークショップが終盤にさしかかり、参加者の体力も限界に近づいてきた頃、私は最後の締めくくりに向けて場を盛り上げるために、簡単な演出を取り入れることにしました。

私が用意したのは手作り感たっぷりの「小切手」です。これを印刷して参加者に配り「エンジェル投資家」を演じてもらうことにしました。そして、どのチームが投資するに値するのかを決めてほしいと、新しい役割も与えました。
その瞬間から会場の雰囲気が一気に明るくなりました。参加者たちは身を乗り出して発表者に質問を投げかけ、最もポテンシャルが高いアイデアがどれかについて熱く議論しはじめました。最後は集計結果をもとにミニ表彰式を開催して、優勝者に手作りの巨大な小切手を贈呈しました。
簡単な小道具を使った場の演出が、参加者の疲れた表情を熱狂に満ちた笑顔へと変え、ピッチをその日のハイライトに変えてしまったのです。
また、今回の演出の効果は、小道具の追加だけでなく、参加者の立場を逆転させたことにも大きな意味があったのではないでしょうか。
立場の逆転がワークショップを非日常的体験にした
この演出が場の空気を明らかに変えたのは、「新たな役割」を与えることで参加者の立場を「評価される存在」から「評価する存在」へと逆転させたからではないでしょうか。もしかすると、それこそがワークショップを非日常的体験にした、決定的な要素だったかもしれません。
いずれにせよ、演出の理解を頭の中だけで行う場合と、実際に目に見えて手で触れられる状態で行う場合とでは、体験に大きな違いが生まれるのは明白でしょう。自分が大きな小切手を手に持って表彰の場に立つ場面を想像してみてください。それだけで気分が高揚してこないでしょうか?
ぜひ、非日常的体験の演出を、実際に手で触れられる小道具を使って試してみてください。できれば立場の逆転も盛り込んで。そうした小さな工夫が、参加者のワークショップ体験に思いもよらぬ変化を生み出してくれるかもしれません。
私にとってファシリテーションは技術以上のアートであり、そのマインドセットも含めて重要な意味を持っています。このブログで紹介した失敗談や成功体験がみなさまの参考になれば幸いです。
文・平岡杏菜
Senior L&D specialist
Moon Creative Labでは、スタートアップを支援するためのプログラムを複数提供しています。ご自身のビジネスアイデアと成長に変革をもたらしたい方はぜひ参加をご検討ください。詳しくはウェブサイトのトップページから。
Share on
Related stories